ポテンシャル枠限定「無限書籍購入制度」をご紹介・自発的な学びの後押しに
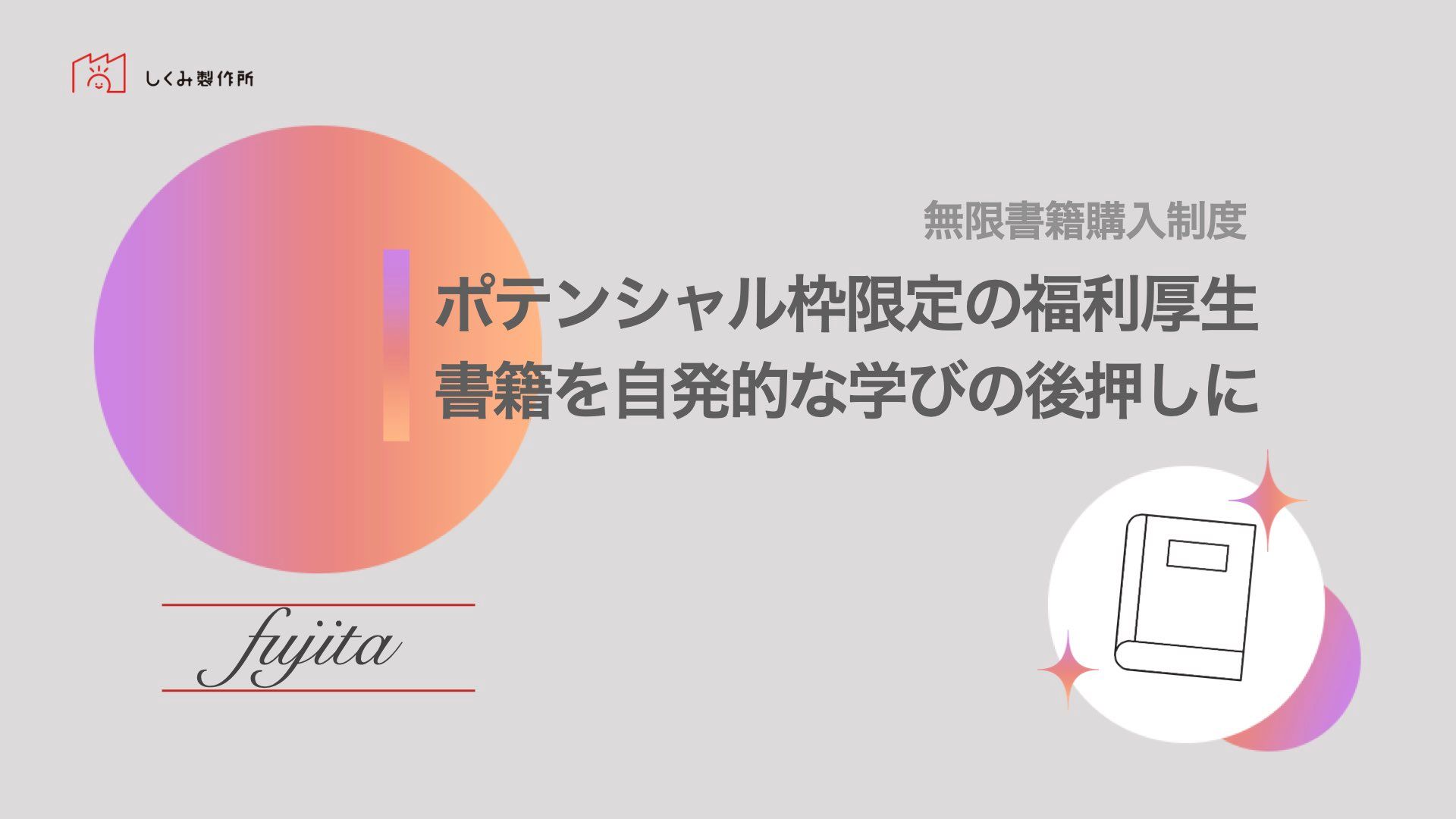
はじめに
こんにちは。しくみ製作所の総務を担当していますfujitaです。
今回はしくみ製作所の福利厚生のひとつである「ポテ枠 無限書籍購入制度」についてご紹介したいと思います。
が、本題に入る前に「福利厚生」と聞いて皆さんはどのようなものを思い浮かべますか。
ひと昔前だと財形や慶弔であったり、住宅等に関する提供が大半を占めていたので、それらを思い浮かべる方も多いかと思います。このような法定外の福利厚生施策については、昨今の働き方改革も影響していると感じており、仕事だけでなく生活との両立の促進や自己啓発を促すもの等への多様化も進んできた印象を受けます。また、皆さんご存じのように、企業によっては採用のインパクトを高める一つの施策としてもユニークなものを発案し、実施しているところも多く見られるようになってきました。

そんな福利厚生ですが、今回はしくみ製作所内でもポテ枠限定である「無限書籍購入制度」について早速みていきましょう。
無限書籍購入制度とは
しくみ製作所では、2020年の秋からポテ枠=実務未経験のエンジニア枠採用を始め、第一号メンバーが入社したのが同年の12月でした。この採用は、中長期的に目指していきたい組織を時間をかけて作っていくために展開され、現在までに10名以上の入社がありました。
無限書籍購入制度とは、そんなポテ枠のメンバーが「勉強に使う目的であれば、会社経費として制限なく書籍を購入できる」というもので、2022年1月から開始されました。自発的な勉強も必要になるであろうし、どんどん自由に本も読んでもらったらいい、ベテランエンジニアからの提案がきっかけとなっています。
実際の声は
この制度が開始された直後にポテ枠を卒業となったメンバーもいるのですが、実際のところの利用率も気になるところです。また、ビジネス書や技術書には多種多様なものがありますが、ポテ枠の皆さんはそれぞれどのようなものを選び、どんな学びを得たのでしょうか。「結構買わせてもらってます!」「恩恵受けてます!」との声も聞かれ、今回は卒業生も含め3人のメンバーの声をお届けしたいと思います。
kinokoさんの場合
- 書籍名「プログラムはなぜ動くのか 第3版 知っておきたいプログラミングの基礎知識」
- 購入のきっかけ
- 当時、自分の興味・関心や学習内容がどうしても実務で使用するようなRailsやTypeScript等に傾きがちな一方で、それらの技術のベースとなる低レイヤーの部分を学習したい、という思いがありました。というのも、これらの技術はあらゆる技術のベースになっており、将来的に他の言語やフレームワークを学ぶ上でも有用であると考えたためです。そのため、まさに自分の知りたい部分を学習できると考え、こちらの書籍を購入しました。
- 活かされたところ
- 正直、現時点で直接的に何かに活かすことができているとは言い難いです。とはいえ、プログラムがメモリーにロードされてCPUによって実行される仕組み等の基礎的な概念を学習できたため、新しい技術を学ぶ際の助けとなるような、いわゆる学習力の底上げとして役に立っていると考えています。まだ書籍内容の全てを理解しきれているわけではないため、これからも折に触れて読み返すことで知識を定着させ、より学習力の底上げとして活かしていきたいです。
- この制度を利用しての感想
- 技術書の購入には多かれ少なかれお金がかかるため、今回のように主だった興味とは別の部分の学習をする際はどうしてもお金のことを考えてしまい、購入をためらってしまうことがありました。ですが無限書籍購入制度を使用することで、実際に購入・学習に繋げることができました。このように個人の学習を後押しする素晴らしい制度だと感じます。
sakitaさんの場合
- 書籍名「マンガでわかる! 仮説思考」
- 購入のきっかけ
- ポテ枠の仕事力でも重要視される仮説思考の基礎的な勉強をしたいと考え購入しました。仮説思考は一般的なビジネススキルでありますが、自分自身は仮説思考が苦手であると自覚していました。しかし、仮説思考の本はどれも活字で説明された小難しい本であり、また、仮説思考自体も最初は理解しづらいものが多いイメージです。そこで、比較的とっつきやすいマンガでわかるシリーズを選びました。
- 活かされたところ
- 購入した本は分かりづらい概念を漫画で分かりやすく説明しており、また、かなり実践的な内容も含まれていたので読んでからすぐに行動することができました。特に、バグの修正ではデバッグをする前から具体レイヤーから抽象レイヤーに視点を引き上げてどこに答えがありそうかを探し当てることに取り組みました。結果、バグ回収のスピードが上がり、仕事力面談でも仮説思考の項目での評価に繋がりました。
***
- 書籍名「プロを目指す人のためのTypeScript入門 安全なコードの書き方から高度な型の使い方まで」
- 購入のきっかけ
- フロントエンドへの関心が高く、業務時間外でTypeScriptを学習をしたいと思っていました。理由は、近年TypeScriptはJavaScriptの完全上位互換として、これからもしばらくはフロントエンドの開発の筆頭として使われていくという情報を得ていたためです。そんな時、有名なチェリー本(「プロを目指す人のためのRuby入門[改訂2版] 言語仕様からテスト駆動開発・デバッグ技法まで」)をモチーフにしたTypeScriptの本がちょうど出版されたので購入しました。
- 活かされたところ
- 購入した当初は個人的な学習に留まっており、業務でTypeScriptを使用する機会は特にありませんでした。しかし、ちょうど1週間ほど前(2022年7月上旬)から社内業務でTypeScriptを使うことになり、前もって学習していたため、周囲の予想よりはるかに早くキャッチアップをすることができました(TypeScriptはJavaScriptを知っていれば学習の敷居はそこまで高くないですが、やはりいきなり使うのと前もって準備しているのではキャッチアップのコストに大きな差が出ます)。業務で使用し始めたばかりなのでまだ大きな成果はないですが、これから本で学んだことをアウトプットしていきたいと思います。
- この制度を利用しての感想
- 興味があることを自由に学ばせてくれる、ありがたい制度だと思います。本来、自分が購入した本2冊は「実務経験の浅いエンジニア」が必ず読むべき本ではないと感じています。仮説思考は「仕事力」の本であり技術の本ではないこと、ベリー本は実務では使っておらず完全に個人的興味で学習をしました(おそらく読むべき本としては実務であるコーディングで活かせる本(オブジェクト指向、綺麗なコードの書き方)が挙げられると思っています)。しかし、これらの本は無限書籍購入制度の対象として認められました。このように本来なら有料で手に取ろうか迷う個人的な興味関心の範囲のものでも承認してもらい、勉強の後押しをしてもらったことで、より学習意欲が高まった気がします。
kawaguchiさんの場合
- 書籍名「リファクタリング」
- 購入のきっかけ
- ポテ枠で毎週実施している読書会の課題本だったことがきっかけです。内容がやや堅いので最初は気後れしてしまいましたが、読み進めるうちに読みやすいコードとは何か?を具体例と共に学べる良書だと気づきました。今は読書会の課題本から外れてしまいましたが個人的に読み進めています。
- 活かされたところ
- 概念的な面では、リファクタリングの重要性を知ることができました。おかげで実際のプロジェクトでも自分の書いたコードを客観的に見直しす癖が少しはついたかなと思います。また具体的な面では、関数の抽出やカプセル化など変更に強いコードをどう書いていくかを学べました。これは自身でコードを書くときにも参考になりますが、他の人が書いたコードを読むときに特に役立っています。
- この制度を利用しての感想
- ポテ枠は日々学ぶことが沢山あり、気になった本を買っていると書籍代だけでも結構な額です。学習のために自己投資は必要ですが、懐事情はやはり気になります。「この本が気になるな、でも今月は色々本買ったからやめておこう・・・」なんて時にも諦めることなく学びへ投資ができるのは無限書籍購入制度のおかげだと思います。またこのような学びの機会に投資をしてくれる会社だと思うとポテ枠としても身が引き締まる思いです。本を選ぶ際も自分はこの本から何を学び取ってやろうかと良いモチベーションになっています。
さいごに
いかがでしたか。しくみ製作所の福利厚生は、単なる採用の目玉になるものやイメージアップを!等と考えられたものではありません。もちろんメンバーとの信頼関係を向上させ、共に気持ちよく働けることを手助けするものの一部ではありますが、メンバーが求めるものと会社が求めるもの双方を明瞭化した上で、現在における最適なものが設計できるよう心がけています。
今回ご紹介した「無限書籍購入制度」も金額の上限を設けないことで、興味関心のあるものを気軽に手に取れるようになってほしい、購入するハードルが下がり少しでも多くの知識を得てもらいながら、実際の業務においても問題解決に活かしてもらえれば、とそのような思いも込められています。そして、その背景にある会社からの支援の姿勢も感じてもらえていたなら、こんなに嬉しいことはないなと感じます。
今後も最適なものを最適なタイミングで、しくみ製作所らしいものを提供していけたらと思います。そして、使ってもらえる環境もしっかり整えていきたいです。
その他の制度については、またの機会に。