第一子の経験を活かして・育休準備と実践の記録「hozum編」
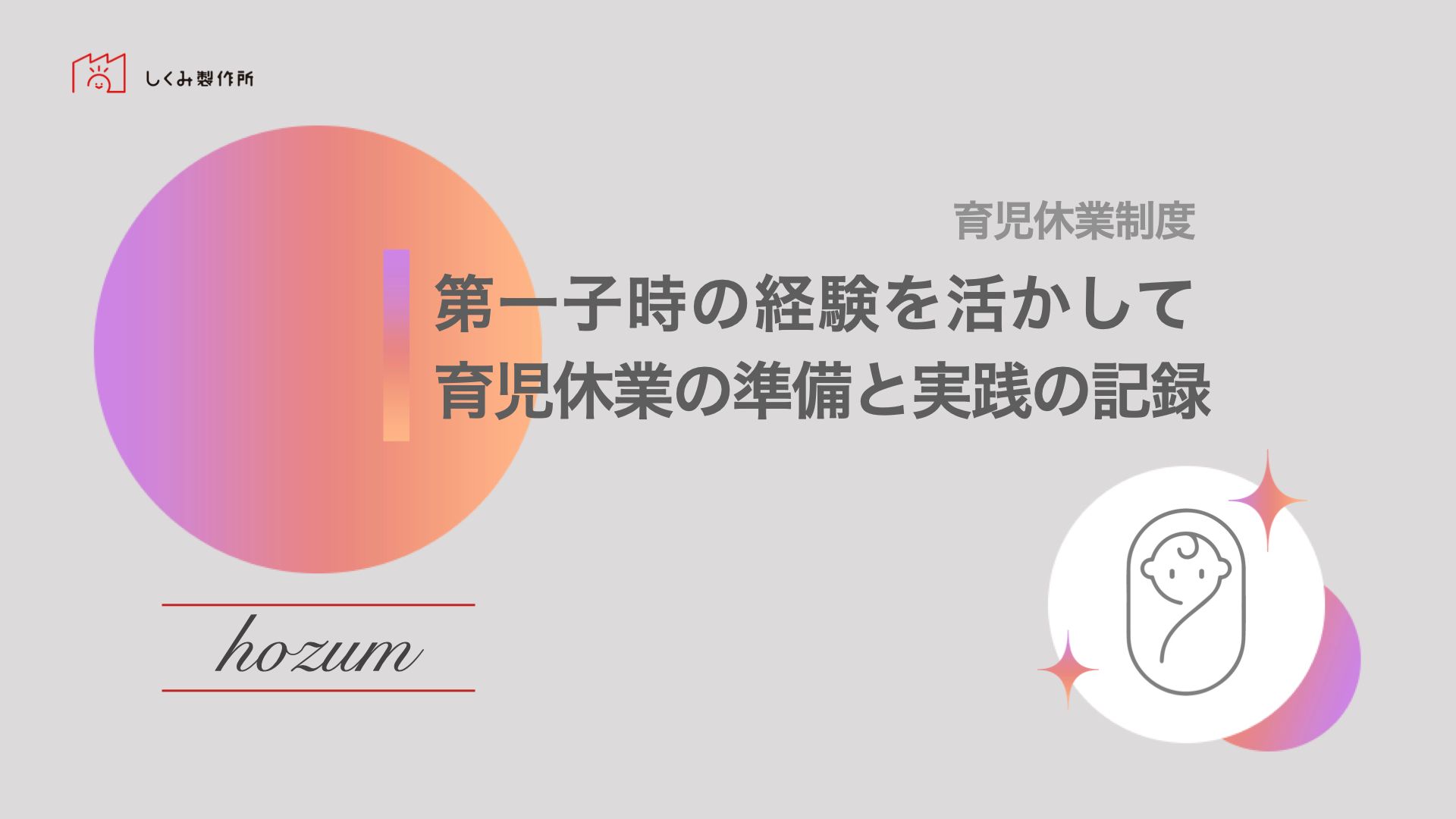
はじめに
こんにちは、しくみ製作所の穂積です。
この度、第二子の誕生に伴い、2024年11月末から2025年2月末までの3ヶ月間、育児休業を取得しました。育休を取るか迷っている方や、これから取得予定の方の参考になればと思い、自身の経験をまとめてみました。
第一子で学んだ教訓
第一子誕生時は育休を取得せず仕事を続けていたのですが、これが想像以上に大変でした。出産前は「両親も協力的だし、なんとかなるだろう」と安易に考えていました。しかし実際には、新生児期は2〜3時間おきにミルクをあげる必要があり、夜中も含めて常に誰かが世話をしなければならない状況でした。
結果として慢性的な寝不足に陥り、仕事のパフォーマンスも下がってしまい、この経験から、第二子誕生時には「必ず育休を取る」と決めていました。
仕事も育児も「チーム戦」
第一子との貴重な時間を確保できた
育休取得の最大のメリットは、3歳になる第一子としっかり向き合う時間を作れたことです。この年齢は愛着形成の重要な時期であり、第二子の誕生で第一子のメンタルに影響が出ることも懸念していました。

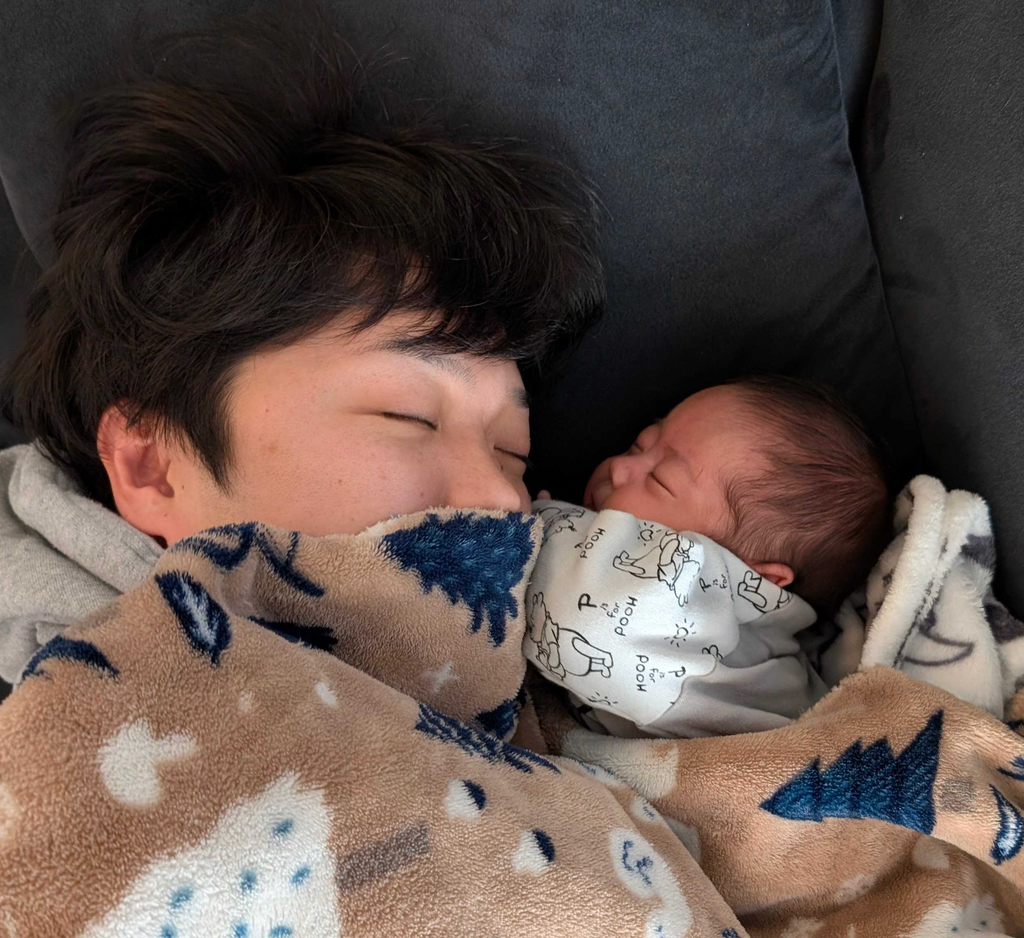

実際、それまで順調だったトイレトレーニングがうまくいかなくなるなどの変化も見られた為、意識的に以下のような対応を心掛けました。
- 家族の会話では第一子を話題の中心にする
- 保育園から帰宅後は、夫婦のどちらかが必ず第一子と遊ぶ時間を作る
こうした取り組みの結果、第一子は第二子に嫉妬するどころか、とても可愛がってくれるようになりました。
夫婦の健康状態が確保できた
新生児の世話は想像以上に体力を消耗します。育休を取得したことで、夫婦で協力しながら最低限の睡眠時間を確保することができました。これは単に体力的な問題だけでなく、精神的な余裕にもつながり、冷静に育児と向き合うことができました。
業務の分散化によるリスク回避
会社にとっても、一人が抱え込んでいた業務を複数のメンバーに引き継ぐことになり、結果として「属人化」の解消につながりました。むしろ「仕事を多く抱えている人ほど育休を取るべき」とさえ感じました。会社全体のリスク分散という意味でも、育休取得は有意義だったと思います。
実践した育児シフト制
育児において何より重要なのは、夫婦ともに連続した睡眠時間をある程度確保することです。子どもの成長に合わせて生活スタイルを柔軟に変更しながら、対応することにしました。
生後2ヶ月までの生活
この時期は赤ちゃんが頻繁に目を覚ますため、夫婦が交代で対応するシフト制を導入しました。
- 夜の3時を境に担当を交代し、それぞれが最低5時間は連続して眠れるように
- 担当時間内は授乳やおむつ替えなど全てを一人で対応
- 非担当者は別室で休み、完全に睡眠を確保
生後2ヶ月以降の生活
赤ちゃんが少しずつ夜間の睡眠時間が長くなってきたため、体制を変更しました。
- 夜間は主に妻が対応
- 日中は私が第二子の世話を担当し、妻が昼寝できる時間を作る
- 第一子の保育園の送迎は私が担当
このように役割分担を明確にすることで、お互いの負担を軽減しながら家族全体の生活リズムを整えることができました。
早期相談によってスムーズに育休へ

育休取得にあたっては、周囲への早めの相談が重要でした。妻の妊娠が安定期に入った頃(出産の約半年前)、会社に育休取得の意向を伝えました。
その後、周囲のメンバーが積極的に業務の引き継ぎに協力してくれました。プロジェクトマネジメントや広報関連の業務など、多岐にわたる仕事を快く引き受けてくれたことに、本当に感謝しています。
育休開始の1ヶ月前には、ほとんどの引き継ぎが完了し、安心して育休に入ることができました。この経験から、育休を考えている方には、妊娠が安定期に入ったらできるだけ早く会社に相談することをお勧めします。
さいごに
今回の育休取得を通じて、新しく生まれた第二子だけでなく、第一子との貴重な時間も確保できたことは、かけがえのない経験となりました。
育児、特に出産直後の新生児の世話は、一人で担うには無理があります。夫婦で協力し、最低限の睡眠時間を確保しながら育児に向き合うことが、子どもにとっても親自身にとっても健全な環境につながると実感しました。
迷っているパパさんたちへ。ぜひ積極的に育休を検討してみてください。育休は単なる「休暇」ではなく、家族の新しいスタートを支える大切な時間です。そして会社にとっても、長い目で見れば必ずプラスになると信じています。