PMへの挑戦と学び・課題解決を追求する道のりで「キャリアの記録〜sakamoto編〜」

はじめに
こんにちは。しくみ製作所に入社して4年が経ったsakamotoです。
私は元々未経験エンジニアとして2020年12月に入社しました。そして2024年4月から現在まで、プロジェクトマネージャ兼エンジニアとしてプロジェクトに参画しております。
今回ブログを書く機会をいただきまして、これまでのキャリアパスを振り返ると共に、現在の業務についてやこれからの展望についてお話しさせていただければと思っています。
これまでの案件での学び
入社してから以下の案件に参画してきました。
①不動産会社社内システムのバックエンドエンジニア (2020/12~2021/4)
入社してから半年弱、まずは社内システムのバックエンドエンジニアとしてアサインされました。こちらは開発部署を持たないクライアントからの受託案件であり、いわゆるエンジニアメンバーは弊社社員のみ(メンバー数も3~5人程度と小規模)でした。
toC向けのシステムのフロント部分も弊社の担当システムでしたが、私はまだそこには力及ばずといった感じで、バックエンドの改修のみを担当していました。
ここでは本当にエンジニアとしての基礎の部分というか、一連の開発フローを理解したり、詰まりがあった時の調査方法やデバッグ方法について学んでいたと思います。具体的な粒度のタスクをもらい、シンプルにその改修を担当していました。
②教育機関向けシステムのフロント+バックエンドエンジニア (2021/5 ~ 2024/6)
2案件目では複数の開発チームを持つ自社開発企業にしくみ製作所という一つの開発チームとして参画させていただき、教育機関向けのサービス開発に関わらせてもらいました。
こちらの案件には3年程携わり、本当にたくさんのことを学びました。
具体的なコーディングについてもそうですが、複数チームでの開発体制があったり、SREチームが存在していたりと、「高品質なサービス提供をし続けるために開発組織がするべきこと」が網羅されている印象でした。
自分にとって平たい言葉にすると、「エンジニアリングの中にこういった仕事もあるのか!知らなかった!」という経験をとにかくこの案件で一通りさせてもらったなと思っており、一気に視野が広がった感覚がありました。
個人としては、粒度が少し荒いタスクをもらうようになったり、詳細設計や調査系のタスクももらうようになりました。またこの案件から、タスクを担当する際に「なぜこれをやるべきなのか」を意識するようになったと思います。
具体から抽象へと課題解決の新たなステージに向かって
上記2案件を経た上で、現在の案件にはプロジェクトマネージャ兼エンジニアとしてアサインされています。

正直なところ、自分はあまりキャリアプランをしっかり練るタイプではなく、自ら強い希望があってプロジェクトマネージャとなったわけではないのですが、ここらあたりの要素が絡み合ったという感じでした。
- 自分のやりたいことと概ね方向性の合う仕事だった
- 今まで関わった人からアサインを勧められることがあった
- 社内において挑戦できるタイミングがちょうどよく発生した
現在は1つのクライアント案件の中で、請負契約でのプロジェクト業務と、保守業務の両方にプロジェクトマネージャとして入っています。仕事内容を細かく説明すると要件定義、プロジェクト管理、ステークホルダーとの調整・・・等々ありますが、自分はシンプルに「目標達成のためになんでもする人」だと捉えています。managerの和訳が「なんとかする人」なこともあり、この捉え方は個人的に腹落ちしています。
元々は飽き性な性格でもあり、何か特定の分野を掘り下げるというよりは広く浅くな性質を持っています。(それにはそれでややコンプレックスは持っていますが。)また、実際に手を動かすことも好きですが、設計図を書く様な仕事はもっと好きだなぁとも感じています。
おそらく「頭を使って問題を解決すること」に関心があり、対象や手段にはそこまでこだわりを持っていなのだと思います。
プロジェクトマネージャの仕事が「プロジェクトの目標達成に向けてなんとかすること」であれば、目標達成という答えに向けて必要なことをなんでもするよ、という業務内容は自分にフィットしているなと思っています。今のところ面白いと思ってやれている感覚もあります。
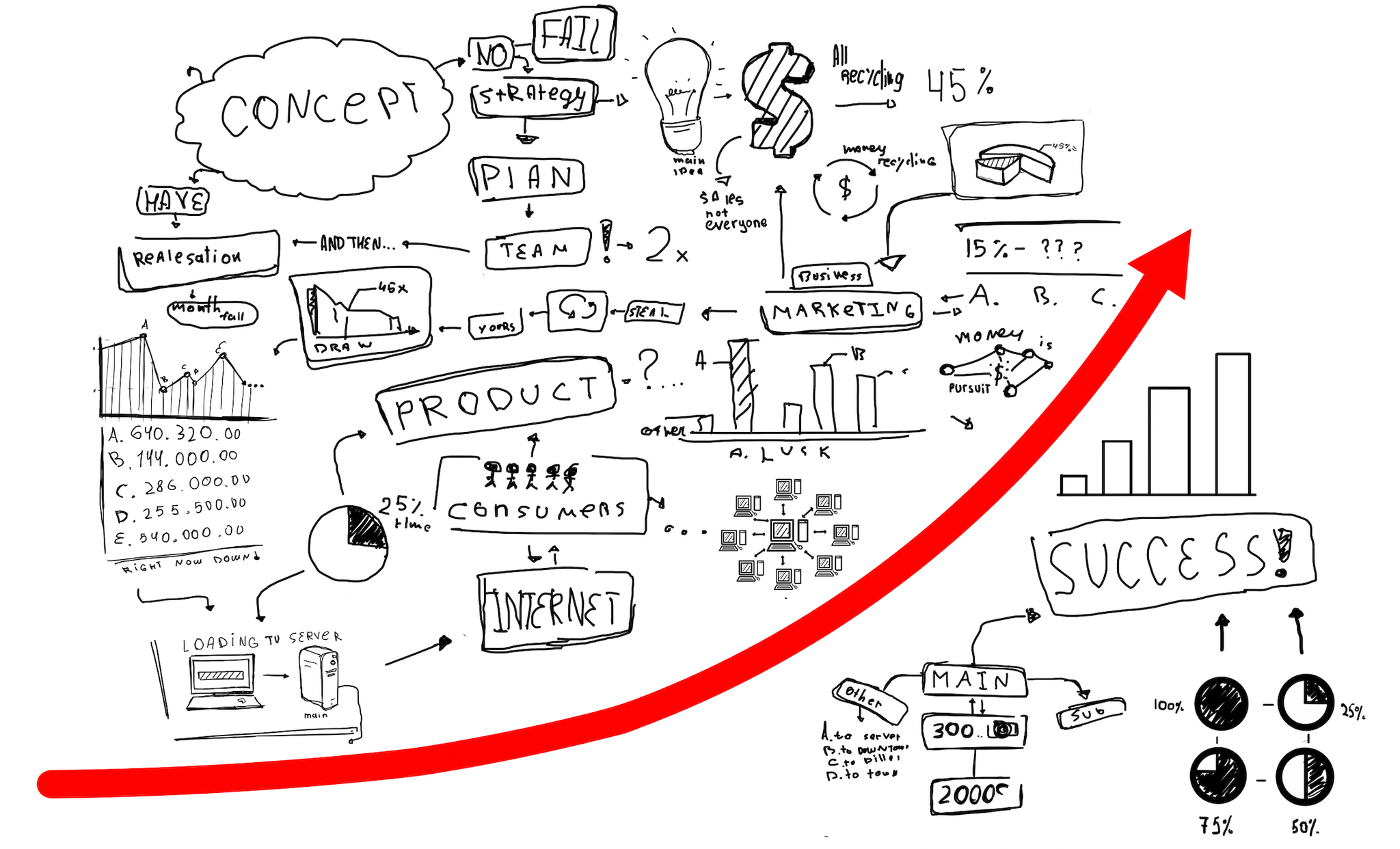
また、今までの業務から何が変わったかというと、具体的な業務内容もそうですが、シンプルに「解決すべき課題の抽象度が高くなっている」に尽きると思います。
これは特にプロジェクトマネージャの仕事だからそうというわけではなく、「具体的な課題を解ける様になると、少しずつ抽象度の高い課題に取り組む様になる」という一般的な業務の性質に起因しているのだと思います。
そうした意味ではあまり新しいことをやっている感覚は自分にはなく、「具体→抽象の流れを、扱う業務の性質が変わる中で繰り返し続けている」というのが近い表現なのかなと感じます。
余談ですが、業務がうまくまわらず逼迫している時、当然に気持ちが滅入ることがあると思います。(自分はそこそこあります。)ですが、この様な捉え方をしていると、「課題が具体的に見えているのであれば、たとえわからなくてもあまり気に病む必要がない」と思え、幾分気が楽だったりします。
抱え込みすぎからの脱却
言うは易し、行うは難しといったところで、前述した「なんとかする」を四苦八苦しながらこなしている、というのが現状です。
課題についてもあげればキリがないですが、一番大きなものとしては「自分でボールを持ち過ぎている」ことだと最近気づきました。ありがちなアンチパターンですね。
これをどちらかというと労働量でなんとかカバーしている・・・という状態で数ヶ月続けていたのですが、あまり健全じゃないなと思い直し、最近は人にボールを委譲していくことで解決を図っています。直近の仕事は極力他のメンバーに依頼し、自分は少し未来の仕事に注力する、というスタンスでシフトチェンジに取り組んでいます。

現在目下改善中、と言う状況ではありますが、「業務進捗に対する分析を行う土台が出来た」という感覚があり、やるべきだったと感じています。
労働量でカバーしていると、順調に仕事が進まない時に原因を特定する方向に思考がいかないんだな、というのを今になって理解してきました。タスクの見積りが甘かったのか、突発的なタスクに対する考慮が不十分だったのか、設計が悪く手戻りが増えているのか・・・、無理やりなんとかしているとこうした分析が出来ない状態になってしまうので、改善が図られず、改善が難しくなるというパターンに陥っていたと感じます。
勿論ゴールから逆算して労働量が必要な時は対応しますが、それを常態化させず、必要な時にポイントで投下するというように、足元で改善を進めていきたいです。
感謝の気持ちを表現すること
具体的な業務手法については改善中ではありますが、スタンスとして現在も実施できているかなと思います。かつ、持続すべきこととして「周りの人に常に感謝する」というものがあります。
なんだか言葉にすると心理的に圧迫感があるかもしれませんが、ありがたいことにクライアント様も含め自然に感謝が浮かぶ人達に囲まれているという恵まれた環境でもあり、「周りの人に自然と感謝をしている」という毎日でもあります。
その上で「感謝を忘れない」ための行動は意識的に行う様にしています。
例えば達成すべきゴールのために必要な観点が自分に複数欠如していた時、それらが矢継ぎ早にフィードバックされることがあります。その時の自分の心理状態次第では、それが本質的に自分のためになることだと理解していても、言われた瞬間に心理的負担を感じることはあると思います。
そうした時ほど、自分は意識的にフィードバックに対する感謝の言葉を口に出す様にしています。「今、辛いな」と思いながら相手には感謝の気持ちを伝える、ということをよくします。にっちもさっちもいかなくなったら辛いですと言ったりしていますが。笑!

対人関係で生じるストレスの多くは「相手は悪くないが、自分は辛く感じた」というケースなので、相手の期待や言葉をポジティブに受け取るために意識的にこの様な対応を行なっています。自分は性格として感情優位な人間なので、その性質をハックして対応している感覚です。(理性優位の人はピンとこない話だと思います。笑)
意識的に周囲に対して誠実であり続けることが、他者を巻き込んで仕事を進めていく上で必要なことだという信念を持っているので、この姿勢については今後も継続していきたいです。
このような心掛けを忘れないようにしながら、当面は自身の余裕を確保しつつ業務をこなし、チームやプロジェクトの改善により目を向ける、という状態を目指していきたいと思っています。
また、目標達成のためになんとかする土台を作りつつ、目標自体を発見・創造する仕事にも慣れていきたいです。仕事を創る仕事の経験はまだまだ浅いですが、そこにも適応していく必要があるなと、日々できることが増える度に強く感じています。
さいごに
キャリアパス、というと計画的・定量的に目標を設定し歩んでいくといった目線が一般的な気もしますが、「自分の性質を知り」、「自分の立場に対する周囲の期待値を把握し」、「自分と周囲を無理なくフィットさせていく」というアプローチが自分にとっては自然なスタイルです。このような形で目の前の業務に取り組んで来た結果、今こんな歩き方をしているよ、ということを今回振り返らせてもらいました。
同じ様な性質の人には何か響けば良いし、異なるスタイルの人には「こんな考え方の人もいるんだ」という参考になれば嬉しいです。
それではまた。