社内ナレッジ共有の新たな試み・変化の速いAI領域を学ぶ「AIお茶会」
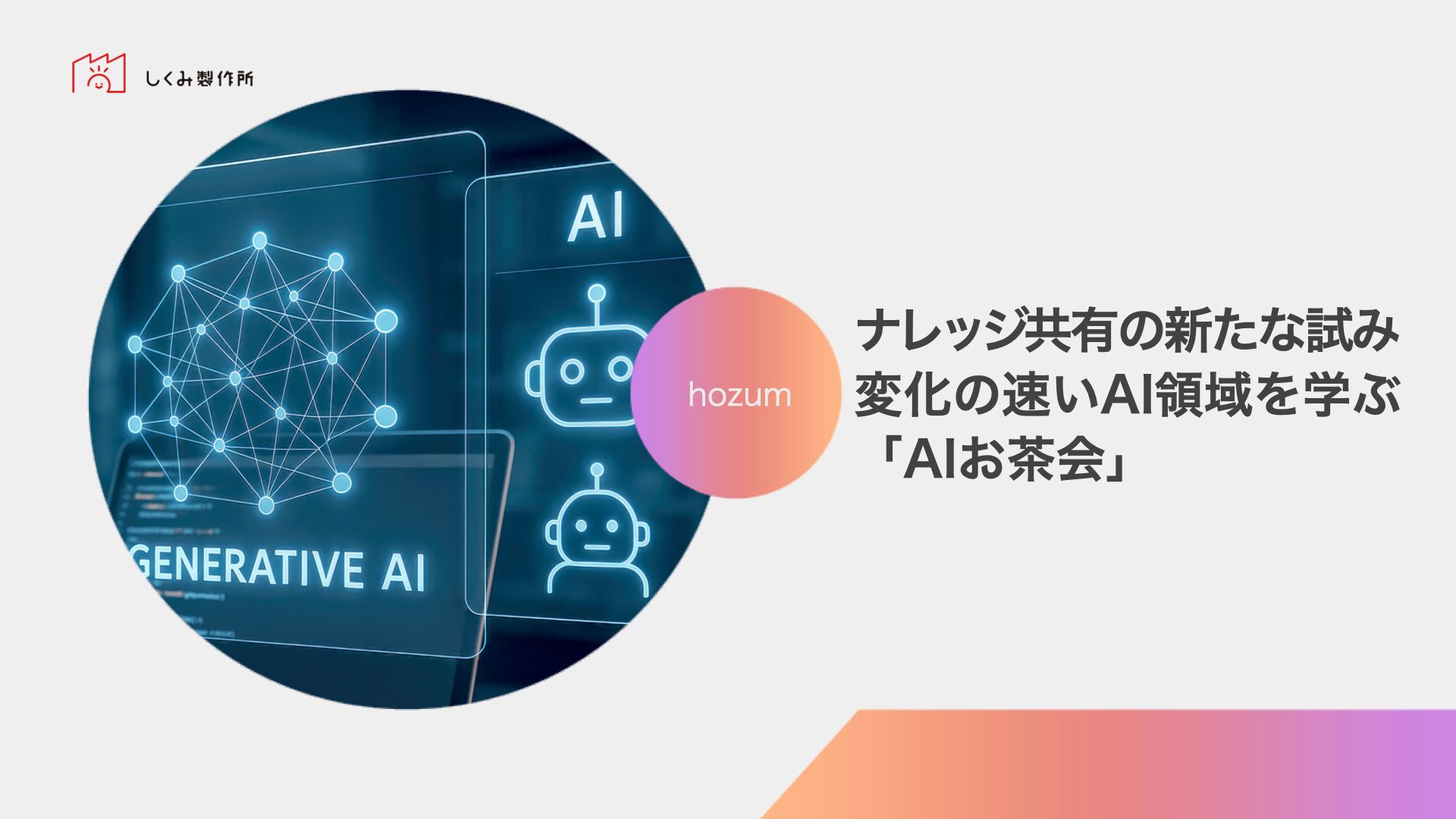
はじめに
しくみ製作所の穂積です。
最近、社内では「今日のClaude Codeの調子はどう?」「Cursorの新機能、もう試した?」といった会話が活発に交わされるようになってきました。こうした日常的なやり取りと並行して、コード生成AIに関する理解を深め、知見を共有するための社内勉強会も開かれています。
今回はその勉強会(お茶会と名付けています)として開催されている「AIお茶会」についてご紹介します。
スピーディーに情報を持ち寄れる場を作る
AIお茶会を始めた理由は非常に明確です。Claude CodeやCursor、GitHub Copilotといったコード生成AIサービスは日々進化を遂げており、そのスピードは驚くほどです。そうした状況の中で、プロダクト開発に関わるしくみ製作所としても、こうした技術の変化をいち早く捉え、継続的にキャッチアップしていくことが重要だと考えるようになりました。
しかし、ここで一つ大きな課題が浮かび上がってきました。コード生成AIサービスの進化スピードが非常に早く、得られた情報がすぐに陳腐化してしまう状況にあるという点です。実際、毎週のように新機能がリリースされ、新しいツールも次々と登場しており、それに伴って使い方のベストプラクティスも刻々と変化しています。
この状況を踏まえ、私たちは「体系的に資料化するよりも、フレッシュな情報をいち早く共有できる場こそが必要だ」と判断しました。つまり、ストック型の蓄積よりも、フロー型のリアルタイムなやり取りを重視するという方針です。これが「AIお茶会」という新たな社内イベントの基本的な考え方となりました。
具体的な実例とノウハウが集まる「AIお茶会」
AIお茶会の最大の特徴は、「事前準備なし」で誰でも気軽に参加できることです。事前に共有されるのはオンライン会場のURLと開催日時のみで、週1回のペースでゆるやかに実施しています。当日は、参加者がその場で話したい話題を自由に持ち寄り、関心の集まったトピックについて対話を深めていく形式を採用しています。

過去の例を挙げると、以下のようなテーマについて活発な議論が交わされました。
- ユーザーの課金情報を調査する MCP サーバーを作ったら捗った話 実案件で顧客データの分析が必要になった際、専用のMCPサーバーを構築することで、従来手作業で行っていた作業を大幅に効率化できた事例を共有しました。
- DevinSearch を活用するとプロンプトの作成が楽になっていいですよ DevinSearchを使うことでリポジトリ全体の情報を元に適切なプロンプトを素早く作成できるようになったノウハウを紹介しました。
また、特定のテーマに特化した「テーマお茶会」も開催しています。例えば「Claude Codeお茶会」では、Claude Codeの使い方に特化して深く議論したり、「○○プロジェクトでのAI活用」として、実際の取り組み事例を共有してもらう場として、該当する参加者に事前に声掛けし開催しています。
さいごに
今回はAIお茶会についてご紹介しました。
AI関連の変化は本当に早く、今後もこのペースは続くと予想されるので、当面は引き続きフロー情報を優先していきます。
あと定型化できそうな部分については「しくみ」として落とし込んでいきたいと思っています。具体的には、デザインシステムのMCPサーバーを会社として整備することなどを検討しています。これにより、個人の知見を組織の資産として蓄積し、より効率的なAI活用が可能になると考えています。
AIお茶会で得られた知見は、単なる情報共有に留まらず、実際のプロダクト開発や業務効率化に直結する成果を生み出しています。変化の激しいAI領域だからこそ、このような柔軟で機敏な情報共有の場が重要だと実感しています。
今後も継続的に取り組みを進化させていきながら、またご報告できればと思います!