AIツール活用の全社導入事例のご紹介
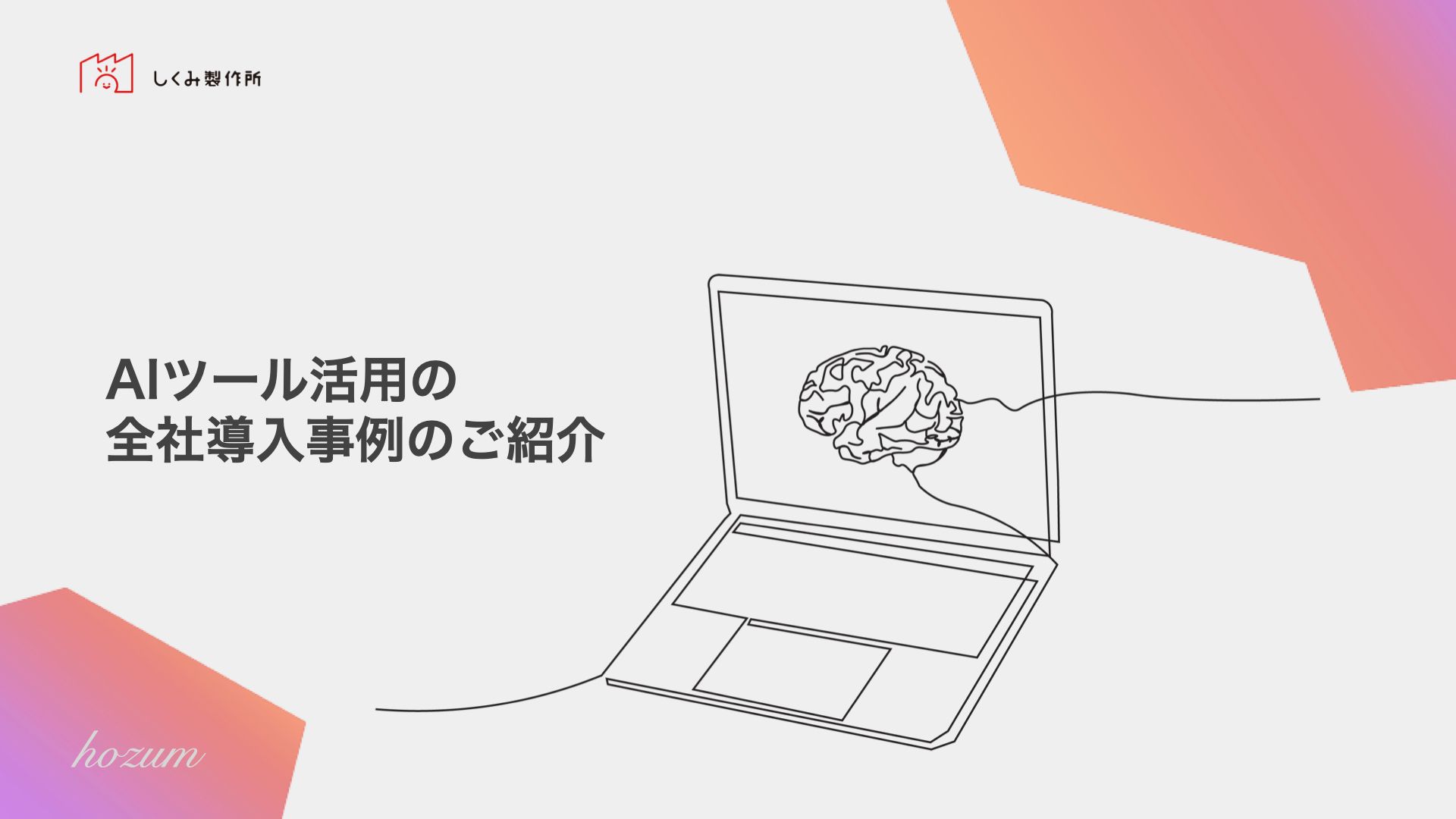
はじめに
みなさん、こんにちは。しくみ製作所の穂積です。今回は、当社におけるAIツール活用の取り組みについてご紹介します。
AI技術の急速な発展を受け、しくみ製作所では全社的にAIツールの導入を推進してきました。その結果、2025年10月現在、在籍する全エンジニアが日常業務で何らかのAIツールを活用しています。
今回は、2025年2月から始めた本格的な全社導入の取り組みを中心に、導入プロセスの構築から運用まで、実施した施策を詳しく紹介します。組織でのAIツール導入を検討されている方々の参考になれば幸いです。
情報漏洩リスクへの対応
企業でAIツールを活用する際、最初に直面するのが情報漏洩リスクです。特に懸念されるのは、入力情報がAIツールの学習データとして利用されることによる情報流出です。
しくみ製作所では、この重要課題に対して以下の2つの取り組みを実施し、セキュアな環境でのAIツール活用を実現しています。
1つ目は、ISMS規定への組み込みです。情報セキュリティハブと密接に連携し、既存のISMS規定にAIツール利用に関する明確なルールを定めました。これにより、全社員が統一された基準でAIツールを安全に活用できる体制を構築しています。
2つ目は、AIツール導入プロセスの確立です。新しいAIツールを導入する際の審査プロセスを確立しました。このプロセスでは、利用希望者とAIハブメンバーの双方が、対象ツールが入力内容を学習データとして利用しない設定になっていることを確認します。この二重チェック体制で、新しいツールも安心して導入できる環境を整えています。
新しいAIツールが利用できる環境の整備
しくみ製作所では、AIツール利用に対して全社的な予算を割り当てています。これにより、メンバーは個人で費用負担することなく、最新のAIツールを活用できます。また、AIツール業界の変化の速さを考慮し、特定のツールに限定せず、メンバー自身が最適なツールを選択できる柔軟な環境を目指しています。
定番ツールとチャレンジ利用枠
定番ツールのライセンス付与として、GitHub Copilot、Cursor、Windsurfなど、エンジニアの間で定評のあるAIツールは、会社の組織アカウントからメンバーへ直接ライセンスを付与しています。これらのツールは一括管理が可能で、メンバーは煩雑な手続きなくすぐに利用を開始できます。
一方で、登場間もないAIツールは組織アカウント作成ができない場合も少なくありません。このような場合に備えて「チャレンジ利用枠」を設けています。このシステムでは、メンバーが一時的に費用を立て替え、後日経費精算することで、実質的な費用負担なく新しいツールを試せます。新ツール導入時は、必ずAIハブメンバーと共に学習データとして利用されない設定になっていることを確認してから利用を始めます。
これらのAIツール利用プロセスを整備したことで、以下の成果を得られました。
- 全エンジニアのAIツール活用
在籍する全てのエンジニアが日常業務でAIツールを活用
- 多様性のあるツール環境
様々なAIツールが社内で利用され、ツールの比較検討や知見共有が活発に行われる土壌が形成
知識の横展開 〜AIお茶会の開催〜

AIツールに関する知識や経験を組織全体で共有するため、「AIお茶会」を定期的に実施しています。
AIお茶会は、気軽に参加できることを最重視しています。特に事前準備が不要な点が大きな特徴で、忙しい業務の合間でも参加しやすい形式です。
会の進行方法
- トピック出し 参加者それぞれが、気になるニュースや共有したい取り組みを自由に挙げます。 例:「Kiroという新しいツールが気になる」「Cursorの新機能を試してみた」など
- トピック選択 挙げられたトピックから、参加者がそれぞれ興味あるものを1つ選びます。自分が提案したものでも、他の参加者が提案したものでも構いません。
- ディスカッション 選ばれたトピックについて、全員で深掘りします。実際の使用感や課題、活用アイデアなどを自由に議論し、知見を共有します。全員が選んだトピックを消化したら、再度トピックを選んで議論を続けます。
AIツール業界は変化が非常に速く、情報の陳腐化も早いという特徴があります。そのため、AIお茶会では最新情報(フロー情報)を重視し、常に新鮮な知見を共有できる場となるよう心がけています。
さいごに
今回は、しくみ製作所におけるAIツール導入の取り組みを紹介しました。
情報セキュリティリスクを適切に管理しながら、変化の速いAIツール業界にキャッチアップできる体制を構築できたと考えています。特に、全エンジニアがAIツールを活用している現状は、組織としての大きな成果です。
AIツールの導入は、単なるツール購入だけでなく、セキュリティ対策、導入プロセス整備、知識共有の仕組みづくりなど、多面的なアプローチが必要です。本記事が、これから組織へのAI導入を検討されている方々の参考になれば幸いです。
しくみ製作所では、今後もAIツールの活用を通じて、より効率的で創造的な開発環境の構築を目指してまいります。